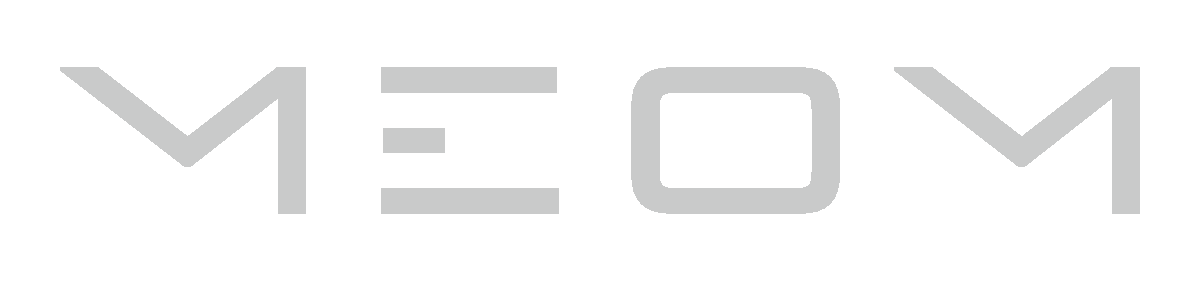25年繰り返されてきた「技術との距離感」
経営者や担当者の方とAI活用の話をしていると
「AIをどう経営に組み込めばいいかわからない」
「社員がAIを使える前提になっていない」
という声を本当によく聞きます。
ただ、幼少期からITに浸かってきた立場から見ると、ここには少し違う感情が湧きます。
「それ、実はこの25〜30年で何度も経験してきた構図では?」という感覚です。
例えば日本では、次のような波がありました。
- 1995〜2000年頃のインターネット普及
- 2000〜2005年頃のガラケー普及
- 2009〜2014年頃のスマートフォン普及
そのたびに企業は「導入」「教育」「業務変革」に向き合ってきたはずです。
にもかかわらず、2025年の今も多くの組織が
- 何から手をつけていいかわからない
- 社員がついてこられるか不安
- ベンダー任せにするしかない
という状態に陥っている。
ここには、単に「AIが難しいから」というだけでは説明しづらい、
ある種の「経験の敗北」が見え隠れしています。
なぜ毎回「初めて」のようにつまずくのか
20年ほど前、情報の授業で起きた小さなエピソードがあります。
トラブルが起きた学校のPCを先生が前にして困っている横で、
生徒側の私は自己解決して先に課題を終えてしまった、という状況です。
おそらく似た経験をした方も多いと思います。
技術の理解度が「教える側」よりも「学ぶ側」の方が高い。
このギャップは、いまのAIでも各所で起きています。
なぜこうしたことが起こるのか。
ひとつの要因は、技術そのものよりも「技術に向き合う姿勢」の差です。
- 仕様をすべて理解してから動きたい人
- とりあえず触りながら学べる人
前者が組織の要所を占めていると、新しい技術に対して組織全体の初動が遅れます。
その結果、デジタル化もDXもAXも、毎回「初めての戦い」のように感じられ、
せっかくの経験が次に活かされにくい構造が生まれてしまいます。
コンサル的に言い換えると、
日本企業は「技術導入のプロジェクト経験」は豊富でも、
「技術への態度・学び方の型」は組織知として蓄積されていない、ということです。
人間のホメオスタシスと好奇心のデザイン
「最低限だけでいい」が組織にもたらすコスト
ガラケーからスマホへの移行期、多くの人が
「今のままで困っていないからガラケーでいい」と感じていました。
この「変わらなくても何とかなる」という感覚は、
企業の中にも根深く存在しています。
- 既存ツールでやりくりできているから、移行は後回し
- 新しい仕組みを導入すると現場が混乱しそうだから、様子を見る
- とりあえず“最低限”使えればいい、深く理解する必要まではない
人間にはホメオスタシス(恒常性維持)の働きがあり、
現状を保とうとする力が本能的に働きます。
変化を避けようとするのは、ある意味でとても自然な反応です。
しかし、経営の視点から見ると
- 技術移行を先送りするコスト
- 社員の「最低限だけ」の理解にとどまるコスト
は、じわじわと効いてきます。
「今はまだ困っていない」ことと
「将来も困らないようにすること」は、まったく別のテーマです。
ここを整理しておくと、
DXやAXの議論は「システム導入の是非」ではなく
「変わりたくない人間の自然な感覚と、どう付き合うか」という
より本質的なマネジメントの議題に変わっていきます。
サイエンスコミュニケーターという“翻訳者”の欠如
技術に対する拒否感をやわらげるには、
「好奇心の火種」を灯す役割が必要です。
その代表的な存在が、サイエンスコミュニケーターのような人たちです。
専門家と一般の人の間に立ち、難しい科学や技術を、
恐怖ではなく興味として受け止められるように翻訳する役割です。
残念ながら、日本企業の内部には
- 技術に詳しいが、非専門家にわかりやすく語るのが苦手な人
- 人に伝えるのは得意だが、技術そのものにはあまり興味がない人
のどちらかが多く、「橋渡し」の役を担える人材が少ないのが現状です。
本来はこの中間に
- ビジネスの言葉と技術の言葉の両方を理解し
- 経営と現場の両方の感情も汲み取りながら
- 新しい技術の可能性とリスクを、具体的な物語として語れる人
が必要です。
もし自社の中にその役割がいないのであれば、
外部のパートナーにその機能を一時的に委ねる、
という発想も立派な戦略です。
重要なのは「技術そのもの」だけでなく
「技術との関係をデザインする人」を組織にどう確保するか、という視点です。
人が技術を使う側に立つための三つの実践
経営と現場に「技術リテラシーの橋」をかける
DXでもAXでも、最初の一歩は
「経営と現場が同じ地図を見て話せる状態」をつくることです。
例えば、次のような問いから始めてみると整理がしやすくなります。
- 経営はAIや新技術に何を期待しているのか
- 現場は日々どのような負荷や制約を感じているのか
- その間にある“見えない前提”や“暗黙の不安”は何か
ここを丁寧に言語化したうえで、
「まずどの業務・どの部門で小さく試すのがよいか」
「成功・失敗をどう評価して学びに変えるか」
といった設計に落としていく。
このプロセス自体が、組織の「技術に向き合う力」を鍛える場になります。
単なるPoCやトライアルで終わらせるのではなく、
毎回の試行を「技術との付き合い方のアップデート」として記録し、
社内の共通知にしていくことがポイントです。
内製するのはシステムではなく「問い」
日本企業は歴史的にITベンダーへの依存度が高いと言われます。
それ自体は悪いことではありませんが、
「わからないことは外部に丸投げする」文化が続くと、
技術と向き合う筋力がなかなかつきません。
ただ、すべてを内製する必要はありません。
むしろ現実的ではないケースがほとんどです。
内製すべきなのは、システムそのものよりも
- 何を解決したいのか
- なぜ今その技術を検討するのか
- どのレベルまで自社として理解を深めておくべきか
といった「問い」の部分です。
この問いが曖昧なままベンダーに依頼すると、
- ベンダー主導の提案に振り回される
- 仕様の細部の議論が目的化する
- 導入後に「想像していたものと違う」と感じる
といった問題が起きやすくなります。
逆に、組織としての問いがクリアであればあるほど、
外部パートナーとの協業はスムーズになり、
限られた予算やリソースを、より本質的な部分に集中させられます。
科学館のような「安全に失敗できる場」を会社の中に
人が技術を使う側に立つためには、
「うまく使わなければならない」というプレッシャーから
一度離れることも重要です。
子どもの頃、科学館や博物館で
よくわからない装置に触れながらワクワクしたように、
大人にも「失敗してもよい好奇心の実験場」が必要です。
企業の中でこれを実現するなら、例えば
- 業務成果を強く求めない、技術お試し用のサンドボックス環境
- 好きなテーマでAIや新技術を触ってみる社内ミニ勉強会
- 成功事例だけでなく「うまくいかなかった試行」を共有する場
などが考えられます。
ここで重要なのは、
「AIを使いこなせる人」だけを称賛するのではなく、
試行錯誤自体を評価する文化をつくることです。
このような場を少しずつ積み重ねていくと、
技術に対する恐怖心や拒否感は次第に薄れ、
「自分たちの手で扱えるものだ」という感覚が育っていきます。
DXでもAXでも、本質は「どのツールを採用するか」ではなく、
人間が技術を活用した仕組みに、どれだけ主体的に向き合えるかです。
過去25年の経験を「また同じ失敗を繰り返す歴史」にするのか、
それとも「技術との関係をアップデートしてきた蓄積」に変えるのか。
その分かれ目は、今日の一つひとつの小さな選択、
そして技術に対してどんな姿勢で学び続けるかにあるのだと思います。
Whitepaper
未在を形にする思考法と実践知を学べるホワイトペーパーをダウンロードいただけます。