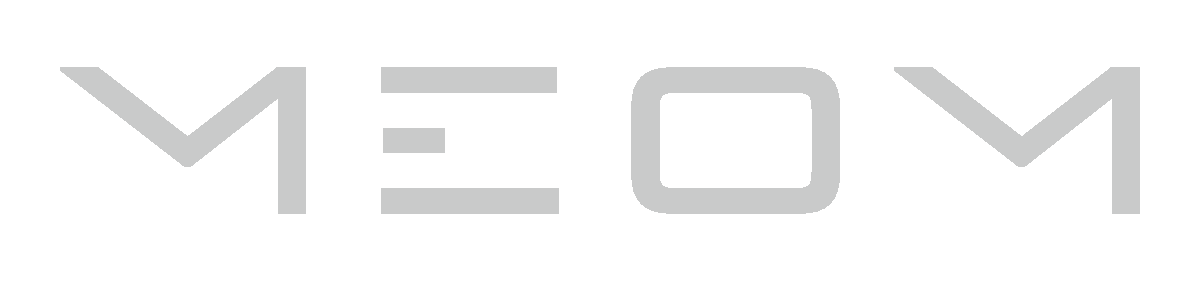AIの研究開発企業でプロダクト企画開発をしている立場として、いつも気になっている問いがあります。
それは「人間は技術によって、どこまで時代の負の遺産から解放されるのか」という問いです。
インターネットは、情報アクセスと表現の自由を大きく開いた一方で、分断や情報過多といった副作用も生みました。
ただ、世の中を劇的に変えるような「巨大技術」だけでなく、中程度のスケールの技術や仕組みでも、確かに誰かを救う「中程度の救済」があり得るはずです。
とくに今は、業界の垣根を超えて、まったく異なる労働文化・経験を持つ人たちが同じ組織で働く時代。
ここにこそ、技術と組織デザインを掛け合わせた「人間にとって負担の少ない世界」の余白があると感じています。
この記事では、人間工学・組織心理・感性工学の視点を行き来しながら、
「人の負担を減らす技術と組織のつくり方」を、少しコンサル寄りの視点で整理してみます。
人間にとって負担の少ない労働をどう設計するか
業務の現場に目を向けると、ビジネスの多くは本質的には「人間の負担を軽くする」ための営みだと言えます。
工数を減らす、移動を減らす、ミスを減らす、確認回数を減らす。どれも、人の負担減という一点に収斂します。
作業負担を軽くする技術と、その限界
人間工学は、身体や認知の負担を減らすために、道具やインターフェースを改善してきました。
椅子の形状、画面レイアウト、ボタン配置、フローの分解。これらはすべて「人が同じ成果に到達するまでのエネルギーコストを下げる」ための設計です。
企業文脈に置き換えると、次のような問いに変換できます。
- この作業は、本当に人間がやる必要があるのか
- 同じ成果にたどり着くまでの「クリック数」「画面遷移数」「確認ステップ数」は最適か
- 人間の集中力・認知負荷を前提にした設計になっているか
こうした問いをベースに、RPAやAIエージェントを組み込むことで、作業負担は着実に減らせます。
ただし、ここで軽減できるのはあくまで「作業としての負担」です。
- 部門間の対立
- 上司との価値観ギャップ
- プロジェクトの空気感や不信感
といった「人と人の関係から生まれる負担」は、単純な自動化だけではほとんど解決されません。
技術で置き換えられない「関係の負担」とどう向き合うか
人間同士の関係性の負担を完全に解消しようとすると、極端な話「業務の100パーセント自動化」が必要になります。
しかし現実的には、技術的制約も、経営判断上のリスクもあり、そこまで振り切るのは難しいのが本音です。
そのためコンサルティングの視点からは、次のような前提整理が重要になります。
- 作業負担は、技術とプロセス設計で削減する
- 関係負担は、組織デザインとマネジメントで軽減する
- どちらに対して、どの程度の投資をするのかを意識的に決める
「すべてを技術で解決しようとしない」ことが、むしろ技術活用の前提条件になります。
中程度の技術開発で中程度の救済を狙うならなおさら、「どこまでを技術に任せ、どこからを人間同士の合意形成に残すのか」という線引きが、プロダクト企画の重要な意思決定ポイントになります。
人間にとって負担の少ない組織とは何か
道具のレベルではなく、組織そのものに目を向けるとどうなるでしょうか。
不仲な集団で、質の高い価値提供を続けることはほぼ不可能です。
一方で、「仲良くしましょう」とスローガンを掲げるだけでは、組織は変わってくれません。
ここで効いてくるのがモチベーションや動機づけに関する古典的な理論です。
モチベーション理論を「組織負担」という視点で読み替える
組織のダイナミクスを理解するために、よく参照される理論を、あえて「負担の少ない組織」という観点で整理してみます。
ハーズバーグの動機づけ・衛生理論では、
満足を生む要因(動機づけ要因)と、不満を防ぐ要因(衛生要因)が分けて考えられます。
- 動機づけ要因:仕事そのものの面白さ、達成感、責任、成長
- 衛生要因:給与、労働条件、人間関係、会社の方針
この枠組みで見ると、
「負担が少ない組織」とは、少なくとも衛生要因が一定水準を満たしており、
そのうえで動機づけ要因にリソースを割けている状態だと言えます。
自己決定理論は、自律性・有能感・関係性が満たされると、内発的動機づけが高まると説明します。
ここから導ける示唆はシンプルです。
- 自分で決められない
- 自分が役に立っている実感がない
- 周囲と心理的につながっていない
この三つが揃うと、その組織は「精神的にかなり負担の大きい職場」になる、ということです。
マクレランドの三欲求理論(達成・権力・親和)、ブルームの期待理論(期待・道具性・価値)も含めると、組織に対して次のようなチェックが可能になります。
- 達成欲求が高い人に、挑戦機会は与えられているか
- 権力欲求が高い人が、健全に影響力を発揮できる場はあるか
- 親和欲求が高い人が、関係づくりを通じて価値提供できているか
- 「努力すれば報われる」という期待を、制度と運用で裏切っていないか
こうした観点を意識的に扱うことで、
「なんとなく居心地が悪い」「なぜか疲れる」という曖昧な不満を、
経営・人事・現場リーダーが共通言語で見つめ直せるようになります。
組織状態の可視化がなぜこんなにも難しいのか
とはいえ、現実には「負担の少ない組織」づくりはうまく進みません。
理由のひとつは、状態把握の難しさにあります。
- 組織サーベイは、設問数が多いと回答負荷が高くなる
- 回答負荷を下げると、得られる情報の精度が落ちる
- 結果のフィードバック自体が、現場の不信感を招くケースもある
経営者やマネージャーからすれば、
「何が本当の課題なのか見えないので、打ち手を打ちたくても打てない」
という状態になりがちです。
その結果、
- とりあえず部門に任せる
- 形だけのワークショップや研修でお茶を濁す
- 結局、日々の業務に追われて手つかずになる
といった構図が繰り返されているのが、現場感覚としての実態ではないでしょうか。
中程度の技術で中程度の救済を狙うなら、
この「状態把握の負担そのものをどう減らすか」が、重要なアジェンダになります。
感性工学で組織のダイナミクスをすくい上げる
ここまで見てきたように技術は「作業負担」を、理論は「概念の整理」を助けてくれます。
ただ、組織が本当に前進するかどうかは、もっと曖昧な領域、
つまり「感じ方」の層に左右されているように思います。
感じ方を無視しない組織設計
感性は目に見えませんが、個人の過去経験と強く結びついています。
同じ出来事でも、
- 安心すると感じる人
- 脅かされていると感じる人
- どうでもいいと感じる人
がいます。
もしこの「感じ方の差」を組織設計の中でまったく無視すると、
制度もプロセスも、ある特定の感覚を持つ人だけに最適化されてしまいます。
感性工学の視点を組織に応用するなら、たとえば次のようなアプローチが考えられます。
- 施策に対する「安心・不安」「期待・諦め」といった感情ラベルを、定量データの横に並べて扱う
- 同じチーム内で、同じ出来事に対する感情分布を可視化し、「なぜ感じ方がここまで違うのか」を対話する
- 新しい制度・ツール導入時に、「誰のどの感性にはプラスに働き、誰にはマイナスになりそうか」をあらかじめ仮説として立てておく
これらは、精密な理論というより、半歩先を照らすための感性レンズです。
「説明可能な感情」というかたちで扱えるようにすることで、
組織のダイナミクスをアルゴリズムのように捉える余地が見えてきます。
アカデミアとビジネスをつなぐ「学び続ける姿勢」
組織論・心理学の世界には、マズローの欲求段階説やエコーチェンバー現象など、
ほかにも多くの理論が存在します。
ただ、時代の変化速度が加速するなかで、それらを現場の意思決定に翻訳する作業はますます難しくなっています。
そのギャップを埋めるには、アカデミアの知見とビジネスの知見を行き来しながら、
自分なりの解釈と検証を重ねる以外に近道はないと感じています。
- 忙しい社会人にとって、学び直しには物理的な障壁が多い
- それでも、理論を学び、現場で試し、言語化して振り返る
- その繰り返しの中でしか、「自分なりの組織アルゴリズム」は育たない
こうして文章にしておくこと自体が、私にとってはひとつの小さな実験です。
中程度の技術と中程度の理論、そして個々人の感性。
その掛け合わせのなかから、負担の少ない働き方と組織のかたちを少しずつ掘り出していければと思います。
Whitepaper
未在を形にする思考法と実践知を学べるホワイトペーパーをダウンロードいただけます。