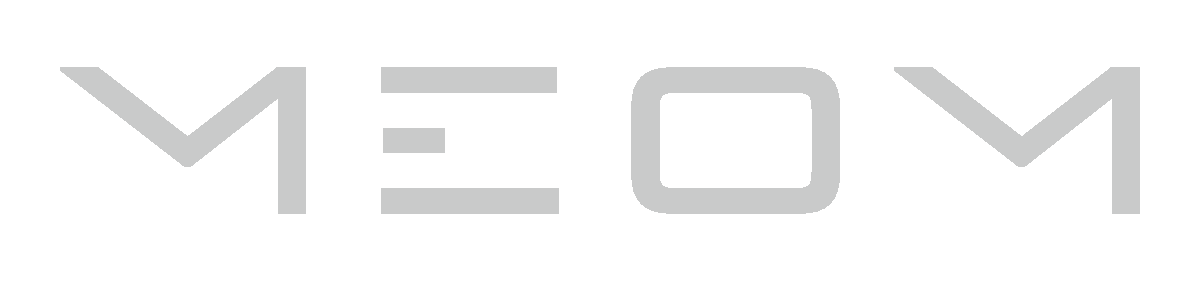新しい事業を立ち上げようとするとき、多くの企業が直面するのは「やってみないと分からない」領域に踏み込む不安と、それでも意思決定をしなければならない現実です。市場は変化が激しく、顧客のニーズも移ろいやすいなか、企画書と会議だけで正解に近づくことはますます難しくなっています。
こうした状況で注目されているのが、デザインとエンジニアリングを横断しながら、つくりながら考えていくデザインエンジニアリングという考え方です。本記事では、その概要と新規事業との関係性、従来の分業型アプローチの課題、そして組織としてどう取り入れていくかを整理します。
デザインエンジニアリングとは何か
最初に、デザインエンジニアリングという言葉が指しているものを、できるだけ誤解のない形で整理します。単に「デザインもできるエンジニア」や「コードが書けるデザイナー」といった職種名にとどまらず、ものづくりの姿勢やプロセスそのものを表す概念として捉えることが重要です。
デザインとエンジニアリングの橋渡しとしての役割
従来デザインは見た目や体験を整える領域、エンジニアリングは仕組みや技術を実装する領域として分けて語られてきました。しかし現代のプロダクト、とくにデジタルサービスでは、見た目と挙動、体験とシステムが密接に結びついています。
デザインエンジニアリングは、この二つを行き来しながら一体で考える姿勢を指します。画面上のボタンひとつを考えるときも、ビジュアルだけでなく、裏側のデータ構造やパフォーマンス、将来の拡張性まで含めて設計していく。逆に、技術選定を行う際にも、ユーザーの操作感や事業側の価値提案を視野に入れて判断する。この橋渡しの役割が、新規事業におけるスピードと質を大きく左右します。
思考法としてのデザインエンジニアリング
デザインエンジニアリングは、特定のツールや技術の名称ではなく、一種の思考法ともいえます。ユーザー視点、ビジネス視点、技術視点を行き来しながら、仮説を組み立て、手を動かしながら検証していくスタイルです。
ここで重要なのは、最初から完璧な設計図を描こうとしないことです。まずは小さな単位で形にし、実際に触ってみて、違和感や問題点を洗い出す。その学びを次のバージョンに反映させていく。この反復の質と速度を高めることが、デザインエンジニアリングの核にあります。
新規事業との相性が良い理由
新規事業は正解の分からない領域に踏み込む営みです。どれだけ市場調査をしても、実際にサービスやプロダクトを出してみるまで本当の反応は分かりません。だからこそ、机上の企画書ではなく、実際に動くものを早い段階で用意し、現場からのフィードバックを得ることが重要になります。
デザインエンジニアリングは「小さくつくって確かめる」ための実践的なアプローチです。アイデアをスケッチからモックアップ、簡易なプロトタイプ、そして本実装へと連続的につなげていけるため、企画と開発の間に生まれがちな断絶を和らげる力を持っています。
新規事業に求められる「つくりながら考える力」
次に、新規事業側の視点から、どのような能力やプロセスが求められるのかを整理します。キーワードになるのは、「不確実性の高い環境での意思決定」と「つくりながら学ぶ」という姿勢です。
不確実性の高い環境での意思決定
新規事業では、市場規模や顧客ニーズが明確に定義されていないことが多くあります。既存事業のように、過去のデータや類似サービスの実績から安全な判断ができるとは限りません。
そのため詳細な長期計画を最初に作り込むよりも、短いサイクルで仮説と検証を繰り返す方が現実的です。最初の段階で決められるのは、「こういう価値を届けたい」「このような課題に向き合いたい」といった仮の方向性までであり、細部は実験の結果に応じて柔軟に変えていく必要があります。意思決定の前提に、不確実性を織り込む発想が求められます。
新規事業の典型的な失敗パターン
新規事業がつまずくパターンの多くは、実は「つくりすぎ」と「つくるのが遅すぎ」の組み合わせにあります。企画段階で細部まで作り込んだ結果、開発に着手する頃には環境が変わっている。あるいは、豪華で多機能なプロダクトを作り込んだものの、ユーザーの目の前の課題とかみ合わず、試す前に息切れしてしまう。
この背景には「失敗してはいけない」「出す前に完璧にしなければならない」といった意識があります。しかし、正解が見えていない段階では、完璧さを目指すほどリスクは高まります。むしろ、粗くても早く出し、学びを得る方が、結果として成功に近づくことが多いのです。
検証と学習のループをどう設計するか
そこで重要になるのが、検証と学習のループを意図的に設計することです。おおまかな流れは、次のような循環にまとめられます。
- 仮説を立てる
- 最小限の具体物として形にする
- 実際のユーザーや関係者に触れてもらう
- 得られた反応やデータから学びを抽出する
- 仮説を更新し、次の一歩に反映する
このループを高速に回すためには、デザインと実装の間に余計な壁をつくらないことが不可欠です。ここでデザインエンジニアリングの発想が生きてきます。
なぜ従来の分業型アプローチでは限界が見えるのか
次になぜ従来の「企画」「デザイン」「開発」が分業された進め方だけでは限界が出てくるのかを、少し具体的に見ていきます。そこから、デザインエンジニアリング的なアプローチの必要性が浮かび上がってきます。
企画と開発の分断が生むコミュニケーションコスト
分業型のプロセスでは、企画担当が要件をまとめ、デザイナーが画面を作り、エンジニアが実装する、というリレー形式になりがちです。一見すると役割分担がはっきりしていて効率的に見えますが、実際には次のような問題を抱えやすくなります。
企画書と要件定義が何度も行き来するうちに、時間だけが過ぎる
仕様が固まる頃には、ユーザーの環境や競合状況が変わってしまう
特に新規事業では、一つひとつの仮説が不確実であるため、紙の上で検討を重ねても、本当に正しいかどうかは分かりません。それにもかかわらず、各工程を順番に進めることで、見直しのタイミングが遅れてしまうのです。
UXと技術制約のねじれ
分業が強い組織では、デザイナーが理想的な体験を考え、エンジニアがそれを技術的な制約の中で現実に落とし込む、という構図になりがちです。このとき、次のようなねじれが生まれます。
- 理想のUXが、工数や技術的ハードルの点で現実とかけ離れてしまう
- エンジニア側からは「実装しやすさ」が優先され、体験が損なわれる
本来であれば、体験と技術制約は同時に検討されるべきものです。ところが、役割が分かれていることで、「先に理想を決めてから、後で何とかする」という流れになりやすく、結果としてどちらの満足度も中途半端になることがあります。
スピードと学習コストのギャップ
分業型アプロセスでは、大きなリリースまでユーザーに触れてもらう機会がないまま進行してしまうことも少なくありません。その場合、学びが得られるのは、すべての工程が終わり、リリースしてからです。
すると、もし仮説が外れていた場合、大きな手戻りが発生します。既に多くの工数が投じられているため、やり直すこと自体が難しくなり、問題を認識しながらも修正できないという状況に陥りがちです。その結果、挑戦すること自体に慎重になり、新規事業のスピードが落ちていきます。
デザインエンジニアリングを核にした新規事業の進め方
ここからは、デザインエンジニアリングの考え方を軸に、新規事業をどのように進めていくかを具体的にイメージしていきます。重要なのは、規模や業種にかかわらず実践可能な「考え方の枠組み」として捉えることです。
小さくつくって試すプロトタイピング
まず押さえておきたいのが、プロトタイピングの位置づけです。プロトタイプは、「完成品の手前の未完成品」ではなく、「学ぶための道具」として扱います。
最初からすべての機能を作るのではなく、価値の核になる体験や機能を絞り込み、シンプルな形で実装します。それを実際のユーザーや社内の関係者に触ってもらい、次のような観点を確認していきます。
伝えたい価値がきちんと伝わっているか
想定していなかった使い方や、つまずきがないか
このように、なるべく早い段階で「小さく恥をかいておく」ことで、仮説のズレを早期に発見できます。修正コストが低いうちに方向修正できるため、結果的に事業全体のリスクも抑えられます。
デザインエンジニアを含むチーム編成
プロトタイピングのループを高速に回すためには、チームの編成も重要です。ここで鍵になるのが、デザインエンジニアのように、デザインと実装の両方を理解し、行き来できる人材を「ハブ」として配置することです。
このような人材は、企画・ビジネスサイドとエンジニアリングサイドの会話を翻訳し、共通のイメージをつくる役割を担います。抽象的なコンセプトをインタラクションや画面フローに落とし込み、同時に技術的な実現可能性も踏まえて調整していくことで、チーム全体のスピードと解像度が大きく向上します。
事業ステージごとに変わるアウトプット
また新規事業のフェーズによって、求められるアウトプットも変わっていきます。ゼロから一を生み出す段階では、「検証のためのプロトタイプ」が中心になります。ここでは、見た目の完成度よりも、仮説を検証するための要素が十分に含まれているかどうかが重要です。
一方、一定の手応えが得られて一から十へとスケールさせていく段階では、信頼性や品質、運用のしやすさといった観点が重みを増します。同じデザインエンジニアリングの発想でも、どのフェーズにいるのかによって、プロトタイプとプロダクトの比重をどう配分するかは変わっていきます。
組織にデザインエンジニアリング文化を根づかせるには
最後に、こうした考え方を個人のスキルにとどめず、組織文化として根づかせていくためのポイントを整理します。新規事業を継続的に生み出すためには、評価やマネジメント、育成の仕組みにも手を入れる必要があります。
評価指標とマネジメントのアップデート
デザインエンジニアリング的な働き方を支えるには、評価の基準を見直すことが欠かせません。完璧な仕様や、美しく整った資料だけが評価される環境では、小さな実験や未完成なプロトタイプは軽視されがちです。
むしろ、新規事業において重視すべきなのは、「学びの量とスピード」です。短いサイクルで仮説検証を繰り返し、その結果を次の打ち手に生かしているかどうか。こうした観点を評価指標に取り込むことで、挑戦と試行を後押しする文化が育まれます。
スキル育成とキャリアパスの設計
デザインとエンジニアリングの両方にまたがる人材は、多くの組織で「例外的な人」と見なされがちです。しかし、新規事業を継続的に生み出すためには、こうした越境型の人材を正式なロールとして位置づけることが重要です。
具体的には、デザイナーが開発の基礎を学べる機会を用意する、エンジニアがUXや情報設計に触れられる場をつくる、といった取り組みが考えられます。また、越境型人材がきちんと評価されるキャリアパスを設計することで、その役割に挑戦しようとする人も増えていきます。
外部コミュニティやパートナーとの連携
最後に、自社の中だけで完結させないという視点も大切です。デザインエンジニアリングの実践者は、国内外のスタートアップやデザインファーム、エンジニアコミュニティなど、社外にも数多く存在します。
こうした外部のコミュニティやパートナーと接点を持つことで、自社だけでは得にくい知見や事例に触れることができます。すべてを自前で抱え込むのではなく、外の知恵を取り込みながら、自社らしいデザインエンジニアリングのスタイルを育てていくことが、結果的に新規事業の成功確率を高めることにつながります。
Whitepaper
未在を形にする思考法と実践知を学べるホワイトペーパーをダウンロードいただけます。